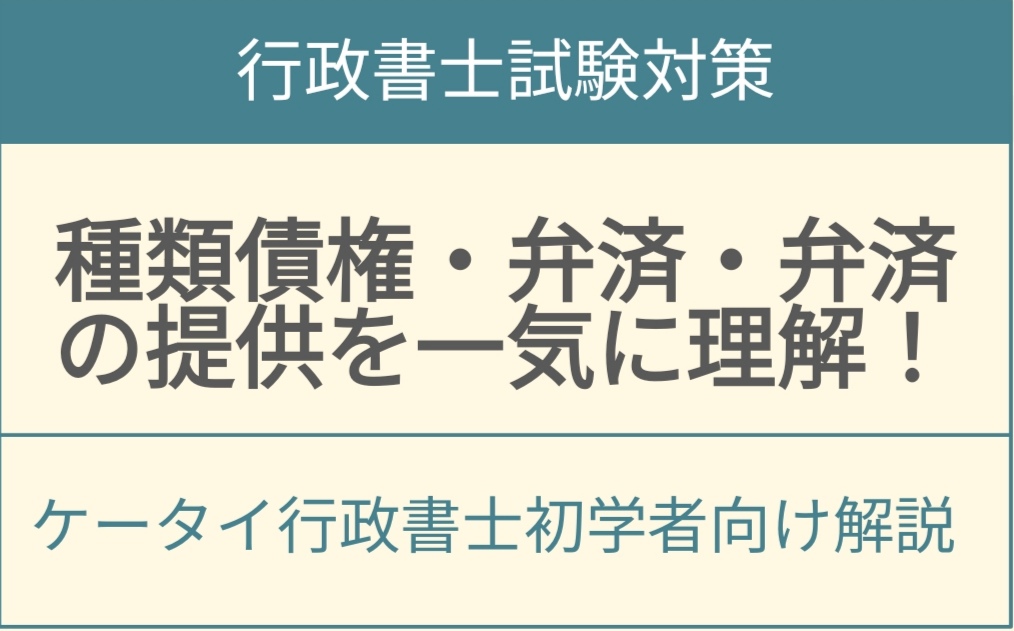民法の学習で必ず出てくるのが「債権」の消滅原因である弁済、そして債務の種類である種類債権です。
今回は、条文ベースのポイントを具体例とともに整理します。
1. 種類債権とは?
① 市場から調達義務
種類債権とは、「種類で定められた物を引き渡す義務」のこと。
例えば「国産コシヒカリ10kgを渡す」という約束です。
もし渡す予定のコシヒカリが倉庫火事で燃えてしまっても、
債務者は市場から別のコシヒカリを調達して渡す必要があります。
→ ポイント:種類債権は「代わりがきく」ため、特定するまで義務は残る。
② 特定物への決定(特定)
債務者が、物の給付に必要な行為(梱包・発送準備など)を完了すると、
種類債権はその物に特定されます。
例えば「この袋のコシヒカリを渡す」と選んで梱包した時点で、
もう他のコシヒカリに取り替えられない状態になる。
2. 弁済と弁済の提供
③ 弁済による債権消滅
弁済(債務の履行)をすると、その債権は消滅します。
例:借金を返せば、貸主はもう請求できません。
④ 外観受領者への弁済
受領権者でないが、見た目上そう見える人(詐称代理人など)に、
善意無過失で支払った場合は有効です。
例:会社の経理担当と名乗る人に支払ったが、実は元社員だった。
外から見れば正しい相手と思えるならOK。
⑤ 第三者による弁済
原則、第三者も弁済できます。
例:親が子の代わりに借金を返す。
ただし、債務の性質上禁止される場合(芸術作品の制作など)は不可。
⑥ 正当な利益がない第三者の制限
関係ない第三者は、債務者や債権者の意思に反して弁済できません。
例:赤の他人が勝手にあなたの借金を返すことはできない。
⑦ 求償権
有効な弁済をした第三者は、債務者に「返して」と請求できます。
例:保証人が返済したら、債務者に請求できる。
⑧ 正当な利益のある第三者の代位
保証人や共同債務者などは、弁済したら自動的に債権者の権利を引き継げます。
抵当権や担保も使えるので、回収がしやすい。
⑨ 正当な利益がない者の代位
ただの友人などは、代位を主張するために「債務者への通知」や「承諾」が必要。
これを対抗要件といいます。
⑩ 弁済の提供による免責
弁済の準備をして差し出せば、債務不履行の責任を免れます。
例:お金を持ってきて「今払います」と差し出したのに、相手が受け取らない。
⑪ 口頭の提供
債権者が受け取り拒否を明言しているなら、
準備して「受け取ってください」と催告するだけで提供とみなされます。
拒絶が明らかなら口頭すら不要。
⑫ 供託
弁済の提供を拒まれたら、目的物を供託所に預けることで債務を消滅できます。
例:家賃を大家が受け取らないので法務局に供託。
まとめ
- 種類債権は「特定するまで代替OK」
- 弁済は「誰ができるか」「代位の条件」が試験ポイント
- 弁済の提供・供託は「拒否されたときの救済策」