■ 地方債ってなに?
かんたんに言うと、
市や県が借金することやねん。
たとえば:
- 市役所を建て替えたいけど、予算が足りへん…
- でも将来の税金で返せばええやん?
→ そんなときに、「地方債(ちほうさい)」を発行して、
お金を借りる(=借金する)のがOKになってる。
■ 誰が許可するの?
お金を借りるってことは、返せんようになったら困るやろ?
だから、国のチェックが入るんや。
- 都道府県・政令指定都市の場合:
→ 総務大臣と協議! - 市町村・特別区の場合:
→ 都道府県知事と協議!
■「協議」って許可とは違うの?
ええ質問やな!
「協議」って書いてるけど、実質は許可がいると思ってOK。
(勝手に借金はできへんで〜ってこと)
まとめ
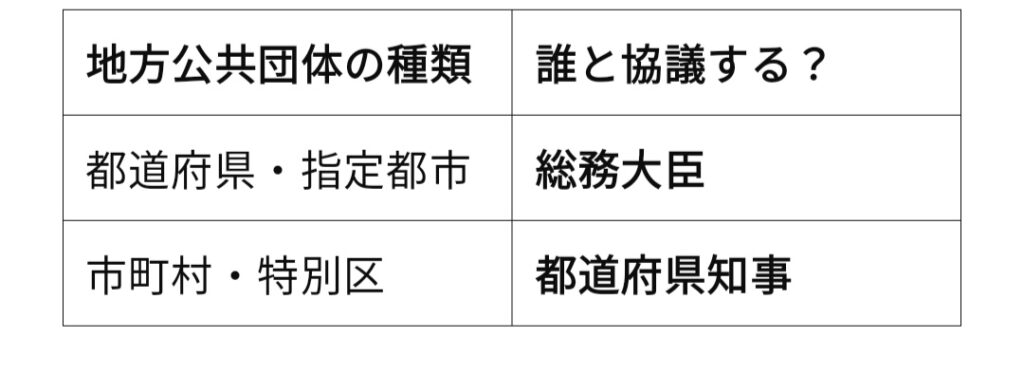
地方債を起こすってどゆこと!?
めっちゃええ視点やな!「地方債を起こす」ってたしかにスケールでかく聞こえるよな。「起こす」って表現、ふつう使わへんしな。
■「地方債を起こす」って、実際にはどういう意味?
簡単にいうと:
地方公共団体(市・町・県など)が、借金の契約を始めることやねん。
■「起こす」ってなんでそんな言い方なん?
法律の言葉ってちょっと古風で、スケール大きく聞こえる表現を使いがちやねん。「事業を起こす」「訴訟を起こす」とかと似てて、
- なにか重大なことを新しく始めるぞ!
- 制度的に、手続きをスタートさせる!
って意味が含まれてる。
■わかりやすく翻訳すると?
「地方債を起こすことができる」ってのは…
市や県が、必要に応じてお金を借りることが法律で認められてる
ってこと。
■イメージで言うと?
たとえば、
- 「新しい学校を建てるから100億円かかる」
- 「そんなに税金でまかなえへん!」
- 「ほな、地方債(借金)を発行して集めよう!」
→ これが「地方債を起こす」ってことやで!
なんか堅苦しく感じるときは、
「カッコつけた言い方してるだけやな」って思って大丈夫(笑)
